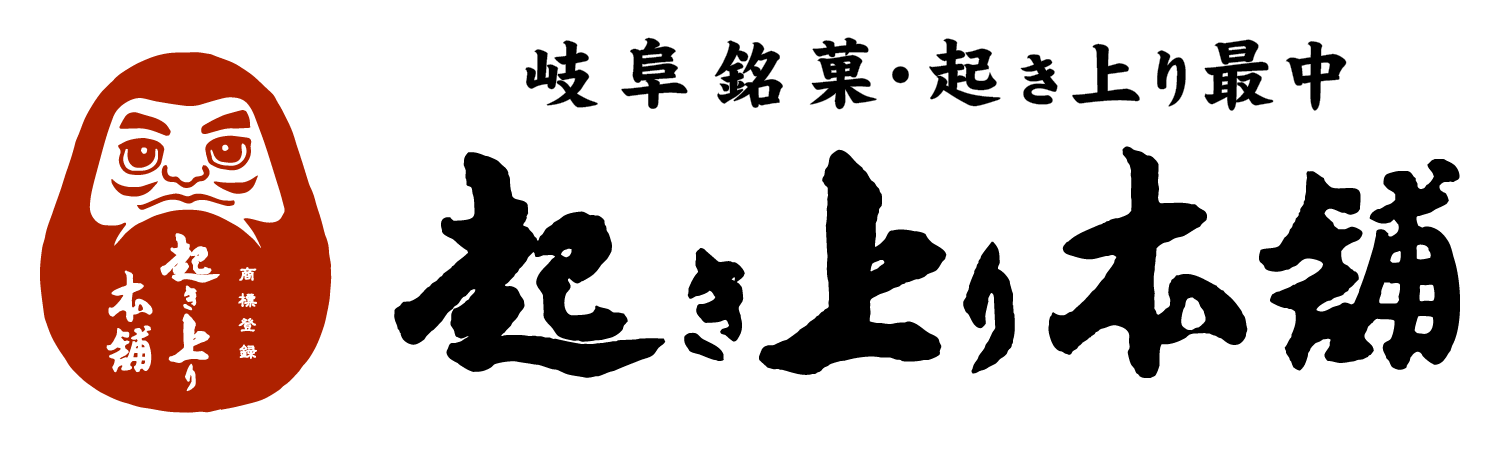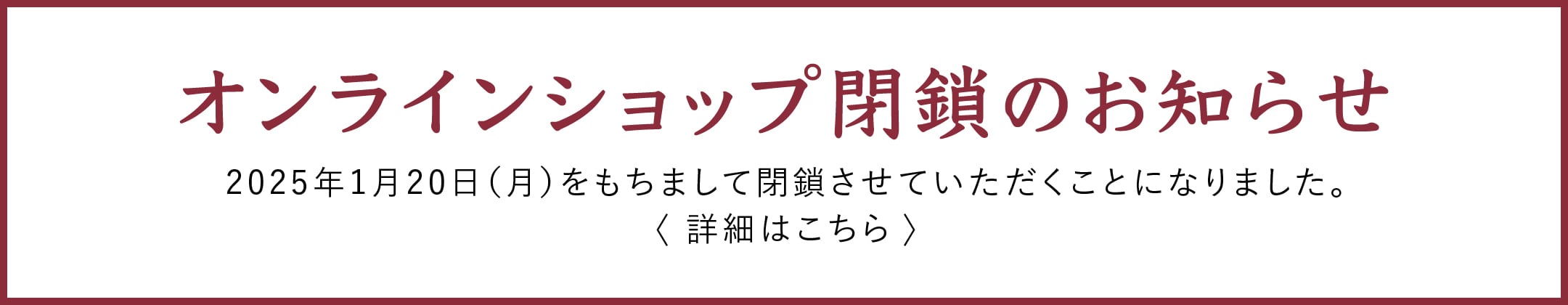- 注文から商品が届くまでどのくらいかかりますか。
- 5営業日以内に出荷させていただきます。
誠に勝手ではございますが、当店は土日祝日はお休みをいただいております。
当店休業中にご注文をいただいた場合、翌営業日に出荷準備いたします。
出荷をしてからの日数はお届け地域によって異なります。
佐川急便のお届け必要日数をご確認ください。
時間指定は、佐川急便の時間帯指定サービスに準じて対応させていただきます。
- のし対応はできますか。
- 一部の商品を除き、可能です。
また、当店では納品書や領収書などの金額のわかるものは一切同梱しておりませんので、ギフト利用の際もご安心ください。
- お届け先の変更/キャンセル/再配達について
- <お届け先の変更>
商品出荷前にご連絡をいただければ、変更対応をさせていただきます。
以下の情報を略さず正確にご連絡ください。
不備がある場合、ご希望のお届け日にお届出来ない事がございます。あらかじめご了承ください。
また、出荷準備を完了してしまったご注文には対応出来ませんのでご了承ください。
◆ご注文者様名:
◆注文番号:
◆ご注文者様電話番号:
◆お届け先お名前:
◆お届け先郵便番号:
◆お届け先住所(都道府県名を略さずご記載下さい。):
◆お届け先電話番号:
<キャンセルについて>
商品発送前であれば、キャンセルを承ります。
商品発送後のお客様都合による返品・交換はお断りさせていただいております。
また、クレジットカード、Amazon Pay以外のお支払方法をご選択の場合は、入金後にお客様都合でのキャンセルは承ることができません。予めご了承ください。
<商品の再配達>
住所不備(アパートの部屋番号不明など)や長期ご不在により、運送会社様での商品の保管期限が過ぎ、弊社に商品が返送された場合、メールにてご連絡いたします。
再配達をご希望の場合は、当店への返送代と再配達代を指定の口座へお振込みいただき、振込確認が取れ次第再発送となります。お振込み金額はメールをご確認ください。(※振込手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承ください)
当店よりメールにてご連絡後、1週間以内にご返信と口座への入金がない場合は、商品はこちらで処分させていただき、再配達不可となりますのでご了承ください。
また、再配達を希望されない場合でも、発送後はお客様都合によるキャンセルとなるため、返金等の対応は致しかねますので、予めご了承ください。
- 注文内容を確認したい/注文確認メールが届かない
- <注文内容の確認方法>
ご注文完了時に配信する「ご注文内容の確認メール」をご確認ください。
また、会員登録をされている方は、マイページでもご確認いただけます。
マイページの「注文履歴」をご覧ください。
<注文確認メールが届かない>
2営業日を過ぎてもメールが届かない場合は、下記の原因が考えられます。
ドメイン設定、メールフィルタ設定されている可能性があります。
shop@okiagarihonpo.jpからのメールを受信できるように、受信設定をお願いします。
迷惑メール扱いやスパムメールへ自動的に移動している可能性があります。一度迷惑メールフォルダ内をご確認お願いいたします。
- お届け商品に誤り、破損があった。
- 商品の品質には万全を期しておりますが、万が一商品が破損、汚損していた場合、またはご注文と異なる場合は、商品到着後7日以内にご連絡ください。
送料は弊社負担で返品・交換をさせていただきます。
また、商品の性質上お客様のご都合による返品は原則としてお受けいたしかねます。
【返品交換連絡先】
〒503-0947
岐阜県大垣市浅草4-62
栄光堂ファクトリー株式会社
起き上り本舗 返品受付係
TEL/0584-87-3550
メールアドレス/shop@okiagarihonpo.jp
営業時間/9:00~18:00(土日祝日休)